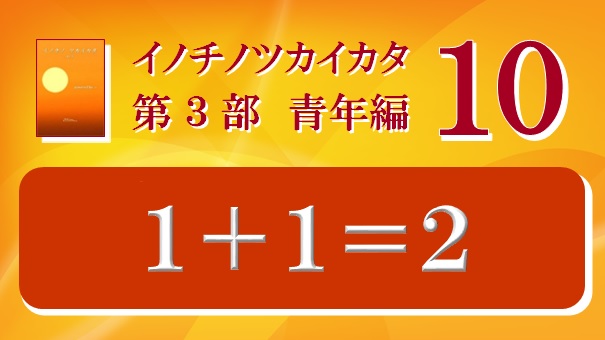第1話から読んでない方はホームからどうぞ。
プルルルル プルルルル…
ガチャッ
「もしもし」
「あッ、私、あんた明日ヒマ?」
「あッ、エミちゃん? 久しぶりやねぇ~ 元気してんの?」
「明日はヒマか?って聞いてんのッ!」
「なんだよ突然、ヒマだったらどうなんだよ」
「よしッ、明日は空けといて! 遊びに行くからさぁ」
「えッ! エミちゃん遊びに来るの?」
「ムーちゃんも一緒、だから明日はあんたの家に泊まるからヨロシク」
「えッ、ムーちゃんも来るの?」
「そうだよ。明日の昼過ぎには着くと思うから。じゃぁね」
プツッ プー プー プー
10年ぶりの会話がこれだ。
といっても別に驚きゃしない。
僕も幼馴染みに電話をするときは、10年ぶりだろうが、100年ぶりだろうが、こんな感じだ。
全通念では、幼馴染みといったら連絡をこまめに取り合ったり、一緒にお出かけしたり、結婚式に呼んだりとかしてるみたいだけど、僕たちは違っていた。
お出かけなんかはもちろん、強烈な用事でもない限り連絡なんかしない。
その強烈な用事ってのには、結婚式が入ってないくらいだ。
一度、結婚式に呼ばれたことがあるけど、ドタキャントラブル要員としての自宅待機というのがあったほどだ。
まぁ、ハイハイしてる頃からの付き合いだし、土日はもちろん、保育園が終わっても日が暮れるまで遊んでたくらいだから、こうなってしまったのかもしれない…
でもだ。
(エミちゃんがムーちゃんと一緒に来るってことは、のっぴきならない用事なんだろうな?)
そう思うと、気が滅入ってたのも忘れて、なんだかワクワクしてきた。
なので僕は、半年ぶりに部屋に掃除機をかけた。
いや、2年ぶりかな???
**********
そして翌日。
ガチャ ドカドカドカ
「よッ」
「おぉ~ッ、ムーちゃんだ。太ったねぇ~」
「農家だからね。ヘヘッ」
「はぁ~、疲れたぁ~、久しぶり~」
「あッ、エミちゃん。おッ、アカ抜けてるねぇ~」
「一応、都会ってところで働いてるからね。でも車って長距離だとホントに疲れる… ムーちゃんを途中で拾わなくちゃならなかったから700キロ以上走ったわ… あ~しんど」
「あらまぁ、それはお疲れのことで」
10年ぶりの再会なのに、先週、遊んでたような感覚だ。
僕の座るテーブルの両脇にドカッと腰を降ろした2人は、缶ジュースをグビグビと一気に飲み干したので、新しい缶ジュースを取りに行こうとしたときだった。
エミちゃんが、唐突に切り出してきた。
「来年、結婚するのよ」
「!」
「えッ、えッ、チョ、チョット待って、エミちゃんとムーちゃんが結婚すんのぉ~ッ!」
シーーーン
「あんたバカか…」
「アハハ、違うよ。僕とじゃないよ。それに僕、結婚してるし、子どもも2人いるよ」
「ええ~ッ!」
「ええ~ッ!」
エミちゃんと僕が、同時に叫んだ。
「なんだよエミちゃん、車で何時間も一緒にいたのに聞いてなかったの?」
「じゃぁ、あんたなら聞いたの?」
「…うんにゃ、聞かないと思う…」
「でしょうが、ほらぁ」
ムーちゃんがへラヘラ顔でジュースを催促してきたので、話を続けながら取りに行った。
面倒くさいのでケースごと。
「でもエミちゃん、結婚の報告のために来たんじゃないんだろ? どうしたの?」
「うん、なんか踏ん切りがつかないんだよね…」
「踏ん切り? 結婚の?」
「うん、けじめっていうか、覚悟っていうかさぁ。なんか区切りみたいなものがね…」
「ふ~ん、でもそれだったら、電話でもいいんじゃないの?」
「電話じゃダメなのよ。私自身がわかってないんだから… だから、あんたとムーちゃんと、面と向かって話したら何かわかるんじゃないかなぁって思って…」
「ふ~ん、でもエミちゃん、それってマイナー・ブルーのことなんじゃないの?」
「バァーカ、誰が妊娠してんのよ! ってか、それを言うならマナティー・ブルーでしょうが!」
「なに言ってんの2人とも、マティーニ・ブルーだよッ!」
「アハハハハ」
腕を上げたかどうかは知らないけど、僕たちの笑いは健在みたいだ。
「でもさぁ、私、区切りっていうことを考えてみるとさぁ、ユウコ先生のこと思い出すんだよね」
「ユウコ先生?」
「うんそう。あのとき、{ムーちゃん、元気でね}って言った言葉…、あれ聞いて泣いちゃったけど、私、寂しくなるから泣いたんだって思ってたのよね。でも実際、みんなと遠くに離れてみても、寂しくなかったんだよね。ムーちゃんはどうだった?」
「僕もエミちゃんと同じだよ。離れても寂しくはないんだよね。不思議と… でもさぁ、あの{元気でね}って言葉が、背中を押してくれた感じはあったよね」
「そうそう、そんな感じだったよね。でさぁ、ずっと地元にいる、あんたはどうなの?」
「僕? う~ん…、ユウコ先生の言葉は確かに沁みたけど、でもそれってさぁ、終わらないって思ってたことが終わってしまうことや、未来への不安っていうモノが、寂しさに置き換わってたんじゃなかったのかなぁ? よくわかんないけど…」
「…あんたってさぁ、たまにワケのわからないこと口走るけど、今のは良くわかるよ」
「うん、よく変なこと口走るけど、今のはわかるわかる」
「お前らさぁ、誉めるか、けなすかハッキリしろよ! 気持ち悪い…」
「アハハ、でもそうよね。10年ぶりに保育園と空き地を見たら、ホッとしたっていうか、安心したっていうかさぁ」
「うん、なんか温かくなったよね」
「あんた流に言えば、{逆が支えてるんだよ}ってとこかな? アハハ」
「やめろよ、テレ臭いから…」
「アハハハハ」
(ちくしょう、からかいやがって… そうだ!)
「そうそう、話しが変わるけど、エミちゃんって可愛くなったよねぇ~」
「な、なに言い出すのよ、き、急に!」
「うん、エミちゃん、キレイになったよね。僕、助手席に乗っててドキドキしたもん」
カーーーーーン
さぁ反撃開始だ。
ムーちゃんの援護射撃もバッチリ決まった。
最強ダブルスの復活だ!
「最初、エミちゃんが疲れた~って髪をほどきながら入ってきたときも、あのアンニュイな感じが、たまらなくセクシーだったよなぁ」
「チョ、チョットやめてよッ」
「うん、それにエミちゃんって肌がキレイだから、ナチュラルメイクがホントに良く似合ってるよ。そしてプルンとした唇に淡いピンクのグロス… すっごく可愛い」
「ホ、ホントにやめて」
(やるなムーちゃん、負けらんねぇぞ)
「それに、そのウエストのクビレがそそるよねぇ。たまらんな、こりゃ」
「やめてぇ~~~~ッ! ハァハァ 降参ッ もう降参するから! ハァハァ」
エミちゃんが叫んだのでボクとムーちゃんは、{このへんでやめてやるか}っていうアイコンタクトを交わすと、エミちゃんが落ち着くのを待った。
(相変わらずだよな… エミちゃん)
たしか中1の夏を過ぎた頃から、急に大人っぽく色気づいてきたエミちゃんは、{可愛い、キレイ}っていう言葉に、極度に反応するようになっていった。
今、そのころと同じように、顔を真っ赤にして下を向いてるエミちゃんがそこにいる。
このとき、僕と同じ想いをムーちゃんも持っていただろう。
あのね エミちゃん
みんな 小さな頃から 思ってたんだよ
エミちゃんは 可愛いってね
ホントだよ
ずっとずっと そして 今も
可愛いと 思ってるんだよ
エミちゃんの すべてをね
ホントだよ
と・・・。
僕とムーちゃんは、もう一度アイコンタクトを交わしたあと、エミちゃんを見守るように、ただ静かに待った。
たぶん2時間でも3時間でも、明日の朝までも静かに待てる…
そんな感覚だった。
(こんな感じで待っててくれたのかな? ケンゾー兄ちゃんって…)
僕はゆっくりとした懐かしい時間の中に浸っていた。
**********
そうやって小1時間が経ったころ、エミちゃんがゆっくりと顔を上げて僕とムーちゃんを見つめてきた。
僕は、エミちゃんのその表情、その眼を見たら、父ちゃんの言ってたことを思い出した。
「人っていうのはなぁ、腹が据わって覚悟が決まったときは、気合の入った表情や血走った眼なんかにはならないんだよ。そんなときは穏やかな表情や、澄んだ眼になるもんなんだよ」
まさに、今のエミちゃんのことだった。
そのエミちゃんが、ゆっくりと口を開いた。
「ありがとう。決めたよ私、来年… 結婚するよ」
「うん、知ってるよ。どうしたの?」
「違うのよ。踏ん切りがついたのよ」
僕とムーちゃんは、顔を見合わせたあと、続く言葉を待った。
エミちゃんはゆっくりと瞬きをすると、声を震わせながら僕たちに話した。
今 私を待っててくれた時間
ありがとう 待っててくれて
その時間が その時間の中に
流れてる大切なモノが
包み込むように教えてくれたの
言葉では・・・
言葉では 言い表すことのできない
大切なモノが 私の中に
ありがとう
待っててくれて ありがとう
エミちゃんの澄んだ瞳からキレイな涙がこぼれ、僕の胸のコップの中にポチョンと落ちた。
このとき僕は、人が持つ{美}というものに、初めて気づいた。
それからどれくらい3人で黙っていたんだろう、気がつくと夕日が差し込んできてる。
するとエミちゃんが、アッサリと打ち切ってきた。
「よしッ、以上! 私の用事はこれで終わりッ!」
「もういいの?」
「うんッ! やっぱり、あんた達に会って良かったよ。私は、やっぱり… あんた達だよ」
いつものエミちゃんだ。
こういったところが、絶大な人気を誇った理由だ。
(エミちゃんのいる組が連戦連勝するのも、うなずけるよな)
そうやって昔の感情に浸っていると、これまたいつもの声が飛んできた。
「じゃぁ、何して遊ぼっか?」
「アハハハハハハハ」
ムーちゃんも、やっぱりムーちゃんだった。
***********
でも、エミちゃんの言った、{やっぱり、あんた達だよ}ってのは、ホントによくわかる。
というのも、いくら幼馴染みといったって、個人個人の関係には、かなりの違いがあった。
僕はエミちゃんのことを、物心がついたときからライバルだと思っているし、エミちゃんも僕のことをライバルだと思っている。
この関係には誰も入れない。
ライバル同士にしか、理解しえないことがあるからだ。
また、僕とエミちゃんだけが持つ、共通認識というものがあった。
それは、
{ムーちゃんにだけは、絶対に敵わない}
というものだった。
中学校を卒業するときにも、
{もし保育園にムーちゃんがいなかったらって思うと、ゾッとするよね}
と、エミちゃんと話したことがある。
今でもそれを考えるとゾッとする。
つまり、僕とエミちゃんにとって、ムーちゃんという存在は{別格}なのだ。
でもムーちゃんは、僕とエミちゃんがそんなふうに思っているとは露ほども知らないし、気がついてもいない。
というより全然わかってない。
ホントに全然わかっていないのだ。
実は、ムーちゃんのスゴイところはココなのだ。
もし僕が、周りからそんな眼で見られたら、天狗になって、それを演じようとしてしまうだろう。
もし僕が、周りからそんなふうに言われたら、有頂天になって、それに流されてしてしまうだろう。
しかしムーちゃんは、ムーちゃんというのは…
いつもムーちゃんでいることができるのだ!
そんなムーちゃんに敵うワケがない。
これは、中学校の頃にハッキリとわかってきたことだった。
ずっと僕は、エミちゃんに対しては、嫉妬したりヤキモチを焼いたりしてきた。
でもムーちゃんに対しては、そのような感情が、これっぽっちも湧かないでいた。
別に見下してるワケじゃない。
それは、テニスを全然やったことのない人が、プロのテニスプレイヤーとテニスをするときの感情とよく似てる。
勝ちたいとも思わないし、負けても悔しくないはずだ。
たとえ、こんな風にテニスが上手くなりたい… 羨ましい… などと思っても、その羨ましさは羨望というものなので、妬みや嫉みなどに変換されることは皆無だろう。
それよりもなにも、プロのテニスプレイヤーと一緒にプレーができること自体を幸運や光栄とも思えるはずだ。
ライバルだなんて思うはずがない。
僕とエミちゃんが持ってるムーちゃんへの{別格}という思いは、そんな感じなのだ。
ムーちゃんには、見えるところ、見えないところで随分と助けられた。
ホントにムーちゃんさまさまなのだ。
…まぁ、エミちゃんもだけどね。
**********
それからも思い出話しに花を咲かせていると、日が暮れてきたようだ。
するとムーちゃんが、ヘラヘラと太鼓腹をさすりながら催促してきた。
「腹減ったねぇ、なんかある?」
「うん、鍋の材料買ってきてるよ」
「なに鍋?」
「ムーちゃんの好きな鳥鍋だよ。んで、シメはエミちゃんの好きなチャンポン麺」
「おぉ~ッ、いいねぇ~」
「じゃぁ、私が作るわ。台所貸して」
「えッ、エミちゃんが作るの?」
「なによぉ~2人ともその眼… 私だって10年間、自炊してたんだよ」
「へぇ~、あのエミちゃんがねぇ~」
「それに、あんたお母さんがいないから、昔っから女性の作った料理が大好きじゃない」
「あッそうか! エミちゃんもおっぱいがペッタンコだけど、一応は女性だもんな」
「うっさいわね~…」
そう言うとエミちゃんは、包丁とニンジンを手にしたまま、自分の平らな胸をマジマジと見つめながらつぶやいてきた。
「ねぇ? なんでこんなにおっぱいがペッタンコなんだろ? 服を着てるときは、カップとか詰め物で少しはごまかせるけど、脱いで鏡を見たら少年みたいなんだよね… 私って」
「もう、少年でいいんじゃないの? っていうか、もうじき中年だけどさ」
「あんたホントにうるさいわねぇ~、ムーちゃん、なんか言ってやんなさいよコイツに!」
「気にすることないよ。おっぱいが小さくたって大丈夫だよ」
「そうよね。やっぱりムーちゃんは、やさしくていいわぁ~。大好きよムーちゃん」
「うん、大丈夫だよ。だって世の中には、マニアってのがいるからね」
「・・・・」
でたッ! ムーちゃんマジックだ。
このムーちゃんマジックの恐ろしいところは、けなしで言っているのか、悪気なく無邪気に言っているのかが、まったくもってわからないところだ。
エミちゃんが、僕に{これはどっち?}という表情を見せている。
数々のマジックを見破ってきた僕も、今回のマジックはわからなかった。
なのでエミちゃんに、{やり過ごせ}っていう感じで目配せをすると、
「ありがとう、ムーちゃん…」
そう言って、首をかしげながらニンジンをザクザクと切り始めた。
まぁ、このときエミちゃんが首をかしげていた理由は、ただひとつ、
{私の結婚相手って、マニアなのかなぁ?}
たぶん、これで間違いない。
これもまた、エミちゃんの可愛い一面なのだ。
でもだ。でもしかしだ!
やっぱりムーちゃんは、いろんな意味で{別格}ということなのだ。
**********
カセットコンロの上で、鍋がグツグツいいだした。
「それではみなさん、めしあがれッ、いっただっきまぁ~すッ」
「あッ、うめぇ。エミちゃん、料理の腕上げたねぇ」
「うん、ホントに美味しい! ってか、お醤油替えた?」
「って、あんたたちさぁ、私の手料理食べるの初めてでしょうがッ!」
「アハハハハ」
そうやって、おバカ3人組で鍋をつついていると、エミちゃんが僕に聞いてきた。
「そういやあんたさぁ、1+1=2って言ってたよねぇ、アレってなんなの?」
「なにが? 1+1=2でしょうが… なに当たり前のこと言ってんの」
「いや違うわよ。小6の遠足のときよ」
「あッ、それなら僕も覚えてるよ。先生が、相乗効果で1+1は、3にでも10にでもなるって言ったら、1+1は2にしかならねぇよって、先生とやり合ったことだろ?」
「{!}あ~ッ、なんかそんなことあったなぁ」
「で、どういう意味なのよ?」
「どういう意味って、そういう意味だよ。1+1=2だよ」
「じゃぁ、相乗効果みたいなもので、5とか10にはならないの?」
「うん、ならない」
「どうして?」
「1+1=2だからだよ」
「…あんた、なめてんの? チャンと教えなさいよ!」
「あ~もう、面倒くさいなぁ~」
「なによあんた! たまにワケのわからないこと言うからこっちが質問したら、いつも面倒くさがって答えてくんないじゃない。だったらワケのわかんないこと言わないでよ!」
「よしなよぉ、久しぶりに会ったんだからさぁ…。でも、今回は面倒くさがらずに答えてやんなよ。そのことなら僕も知りたいしさ。なッ?」
「わかったよムーちゃん… チョット待ってて頭を整理するから」
(僕とのダブルス組を解消して、エミちゃんと組みやがったな? ちくしょう)
僕は少し眼をつぶって、誤ったことを言って2人を迷わせないようにと、注意を払って話しを切り出した。
「まず、イコールの両極は、必ず一致するっていうことを覚えておいてくれる?」
「うん」
「それじゃぁエミちゃん、1+1が2じゃなくて、5になるっていうことは、え~っと、対極が、1+1+3とか、1+1+1+2っていうことになるんだよね?」
「うん」
「もしくは、1+1の1が、ホントは2や3なのに、その人や周りには、1に見えてるっていうことかも知れないんだよ。それに隠れた+1、なんかが、あるのかも知れないしね」
「うん」
「もう少し、わかりやすく言うと、H2+Oって、何になる?」
「H2Oだから水よね。でもそれだったら、1+1=1なんじゃないの?」
「そこだよ、エミちゃん」
「えッ、何が?」
「1+1=2っていうのは、例え、なんだよ」
「例え?」
「そう、例えだよ。1+1=2っていうのは、H2+O=H2Oのことなんだよ」
「よくわかんないんだけど…」
「エミちゃん? H2+Oって何になるって言った?」
「H2O…{!}あッ、わかった」
「なに? エミちゃん」
「もし、1+1が、3とか4になるんだったら、H2+Oが、水以外のモノになるっていうことだ! そんなのありえないよ。そうだとしたら、テレビも車も電話もパソコンも全部できないってことだもん」
「そうだよ。そこがこの1+1=2の意味の入口だよ」
「入口?… {!}あッ、コレって、原因と結果、因果応報のことよね?」
「ご名答! さすがはエミちゃん」
「でも、1+1がホントに1+1なのか? その1が、ホントに1なのか? 隠れた+1はないのか?って考えたら、メチャクチャ複雑で難解な法則だわコレ…」
「エミちゃん!」
「えッ… な、何?」
僕は真剣な眼つきでエミちゃんを見つめ、重々しく言葉を続けた。
「複雑に… してるんじゃないのかなぁ? 難解に見えてるんじゃないのかなぁ? ホントはもっと簡単に見たり、ずっとシンプルにやってもいいんじゃないのかなぁ?」
(エミちゃんならわかるはずだよ。いや、わかっているハズだ!)
その想いはスグに伝わった。
エミちゃんの眼が、パッと開いて僕に飛んできた。
(そうだよエミちゃん… ムーちゃんだよ、ムーちゃんなんだよ)
僕とエミちゃんは、確認し合うように小さく頷いた。
すると、だ。
「ねぇ、おなかいっぱいになったから、お風呂入ろうよぉ」
ムーちゃんだ!
「プッ、アハハハハハ」
「えッ、なに2人とも笑ってんの?」
「アハハハハハハ、コレだ、コレだッ! ムーちゃんはコレなんだよ。アハハハハ」
「アハハハハ、そうそう、コレなのよ! ムーちゃんってコレなのよ。アハハハ」
「そうだよ。知っての通り、小さな頃から僕は、おなかいっぱいになったらお風呂だよ。そんな当たり前のこと、なにが面白いの?」
「アハハハハハ」
「わかったわかった、今お風呂沸かすからチョット待ってろ。アハハハ」
「私が沸かすよ。アハハハハ」
「えッ、お風呂沸かすのが楽しいの? それなら僕が沸かすよ」
「ギャハハハハハハハハハ」
とまぁ、お風呂から上がってからもワイワイガヤガヤ、くだらない冗談やロクでもない話をくっちゃべっていた。
**********
すると今度はムーちゃんが質問をしてきた。
「たしかさぁ、高校卒業するときに遊んでたら、{類は友を呼ぶ、しかし、染まる者もいれば、そぐわない者は出ていく}って言ってたのは何? どういう意味?」
「それ… メチャクチャ面倒くさいんだけど…」
「あ~ッ、私も思い出したぁ~、教えて教えて! 簡単でいいからさぁ」
2人が僕のことをジ~ッと見つめてる。
(こりゃ、今日は言わないと、済ませてくんないな…)
なので僕は、{AさんBさん・桃太郎・3つの常}のことを手短に説明すると、
「あとは、それを使って考えていけば2人ならわかるよ」
そう言って、2人に投げて放ったらかした。
ホントに面倒くさかったからだ。
「でさぁ、動機と表現が、でも、それで類に引っ張られても… それで染まった場合は、でも、それって本心じゃなかったら… じゃぁ動機の動機じゃないの? このとき一致してなくても…etc.…etc.…etc.」
1時間ほど僕が黙って見ていると… やっぱりだ。
「ふあ~ッ、エミちゃん疲れたよぉ、もう寝ようよぉ、お布団はどこ?」
「隣の部屋だよ」
「なに教えてんのあんた… ほらムーちゃん、まだ9時よ。夜はこれからじゃない!」
「農家の朝は早いんだよ。健康サイクル… リズムだよ。ふあ~ッ」
「明日は農作業なんかないでしょ! 明日、助手席でいっぱい寝かせてあげるから大丈夫だってば! ええクソ、起きんかコラッ! それに健康サイクルのリズムがあるヤツが、そんなに太るワケないじゃない! 起きろぉッ!」
「アハハ、エミちゃん勘弁してやんなよ。ほらッ、ムーちゃんもそんなとこで寝ないで隣の部屋に行けよ。ほらッ」
「ふぁ~い、おやすみ~」
「え~ッ、ホントに寝ちゃうのぉ~… じゃぁ、あんた付き合ってくれる?」
「やだ!」
「ほらぁ~、つまんなぁ~い」
「エミちゃんも疲れてんだから、もう寝ろよ。寝不足で事故でも起こしたら大変だよ」
「え~ッ、せっかく面白くなってきたのにぃ~」
「い・い・か・ら・寝・ろッ!」
先に寝てしまったムーちゃんを挟み、電気を消して川の字になった。
するとその真っ暗な中、エミちゃんが神妙な声で話しかけてきた。
「ねぇ、結婚とか私の旦那になる人のことは、もういいんだけどさぁ…」
「ん? どうしたの?」
「私、赤ちゃん産んだら、チャンとおっぱいが出るかなぁ? ねぇ?」
(…知るかッ!)
**********
ってなワケで、次の日。
エミちゃんが昨日の残りでチャッチャと作ってくれたチャンポン麺入り野菜炒めを食べながら談笑していると、あっという間にそのときがやってきてしまった。
「さぁ、ムーちゃん、帰ろうか」
「うん、そうだね」
車に乗り込んだ2人を覗き込むと、2人がテレ臭そうに語りかけてきた。
「{元気でね}…だよ!」
「{大丈夫! どこに行っても何をしてても、きっと大丈夫ッ!}だよねぇ!」
「・・・・」
(コイツら… やっぱりか…)
「お前らさぁ、そんなおセンチなこと言ってて恥ずかしくねぇのか?」
「そりゃぁ恥ずかしいわよ。ねぇムーちゃん」
「うん、恥ずかしい恥ずかしい。もう二度と言わない」
「アハハハハハ」
「でも、どんな理由かは知らないけど… あんたも… そうなんでしょ?」
「・・・・」
コクリ
僕はもう、黙って頷くことしかできなかった。
そして、
「じゃぁ、またね」
と、次いつ会えるかはわからない{じゃぁ、またね}を交わした。
いつものように…
僕は、2人が乗った車のうしろ姿を見送りながら、
(やっと踏ん切りがついたよ。僕もやっぱり、お前たちだよ)
そう思っていた。
**********
【質問】
1+1=2 ⇦コレヲミテ アナタハ ナニヲ カンジマスカ?
**********
【青年編《10》1+1=2】おしまい。
【青年編《11》さよなら】へ